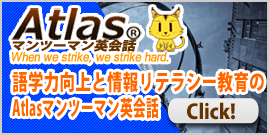|
ついに「大退職時代」がやってきた…!米英で「あえて職に就かない人」が急増中
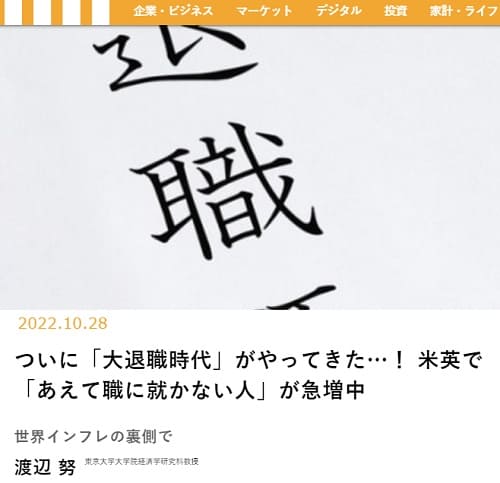
(出典:2022年10月28日 現代マネー)
昨年夏頃から、アメリカやイギリスでは「大退職時代(The Great Resignation)」と呼ばれる、人々が会社を自主退職する動きが起きています。
The Great Resignationは、1930年に始まった「世界大恐慌(The Great Depression)」を真似た造語ですが、当時のルーズベルト大統領は「ニューディール政策」で公共事業を始めましたが、結局、経済政策として景気を回復することはできませんでした。
世界中で続きた世界大恐慌は、第二次世界大戦後まで15年もかかり、それから急激に景気回復が始まっています。今回、多くの人々が自ら無職になって、半自給自足の生活を覚悟するようになりつつあります。
今後の資本主義の在り方を変化させる転換点になるのは間違いなく、勘の鋭いアメリカ人たちが景気後退の前に「リバタリアン的な生活」に慣れるように準備しているように思います。なぜかと言えば、雇用統計は市場予想をはるかに上回っているからです。
12月の米国失業率 前月から改善し3.5% 就業者数も予想を上回る
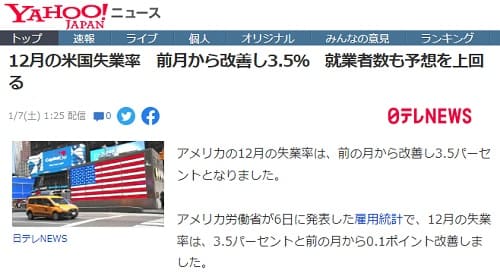
(出典:2023年1月7日 Yahooニュース)
2022年12月の雇用統計は、就業者数が前月から22万3000人も増えており、市場予想よりも2万3000人も多く、失業率も3.5%と50年ぶりに記録を更新しています。しかし、バイデン政権がデータを改ざんしているのは明らかで、誰も公表された数字を信じていません。
また、平均時給も前年同月比で4.6%も上昇し、アメリカでは深刻な人手不足を背景に企業の間で人材を確保するための賃金の引き上げ競争が繰り広げられているのがわかります。しかし、賃金が上がっても人々は会社で働こうとはしません。
さらに、7月~9月の経済成長率(GDP)は2.6%で4月~6月を上回っており、日本の1.6%よりもコロナからの復興が進んでいるのがわかります。つまり、アメリカの景気後退懸念はかなり和らいだ印象があります。
浅い後退か大不況か、世界経済の「最悪シナリオ」 23年は異変の大波が実体経済に押し寄せる番だ

(出典:2022年12月19日 東洋経済ONLINE)
ところが、半数以上のエコノミストが「2023年のアメリカが景気後退に入る…」と予測しており、浅い後退か大不況か、世界経済のシナリオはまだはっきりしていません。実際に、大企業を中心に一斉に大量リストラを実施しています。
巨大IT企業のアマゾンやフェイスブック(メタ社)は当初のがリストラ対象者を約2倍に増やし、セールスフォースは全体の1割に当たる社員をリストラすると発表しています。衣類や外食産業などの業種でも人員削減が発表されており、正に「大辞職時代」が起きています。
最もリストラしているのがマクドナルドですが、なんと20万人がその対象となっています。しかし、アメリカは極端な人手不足に陥っていると報道されており、しかも失業率が低く、賃上げも順調に進んでいるとされています。
アメリカの景気はコロナ騒動から回復しているように見えますが、人手不足なのは特定の職種に限られているということです。
FRBによる政策金利の上昇で、賃金が上がらないIT関連や不動産、金融、食品などインフレの影響を受けている業界は不景気ですが、太陽光発電やEV、宇宙関連事業、観光、そしてAIを中心とした最先端技術関連産業は景気が回復しています。
つまり、以上の業界で専門的な知識や技術を持っている人材は転職しても簡単に仕事が見つかりますが、単なる営業やプログラマーは社会から完全に干された状態にあります。しかし、このまま無事で済むとは到底思えません。
米国が喜ぶ岸田首相の「安倍化」加速している事情 日本の新たな安全保障・防衛戦略が示すこと

(出典:2023年1月13日 東洋経済ONLINE)
アメリカという国は、これまで10年に1回のペースで他国に侵攻することで、経済を刺激して不景気から脱却してきた過去があります。現在も、ウクライナ戦争で大量の軍事兵器や装備品が製造されています。
先日、訪米した岸田首相も大量のトマホーク巡航ミサイルを購入すると発表しました。リストラされたアメリカ人たちは、「戦争経済」でこれから景気がいい会社や関連会社で仕事を得ることになるかもしれません。
しかし、労働力の需給が調整されるのはいつになるのか、その前にアメリカ発の金融恐慌が起きる可能性もあります。繰り返しますが、1929年のウォール街大暴落から始まった世界大恐慌は回復するまで15年もかかりました。
自ら会社を辞職したアメリカ人たちはそのことを察知しており、すでに半自給自足生活を始めているように思います。わざわざ「大退職時代」と各メディアが報道している以上、これまでの常識が通用しないのは確かです。
| 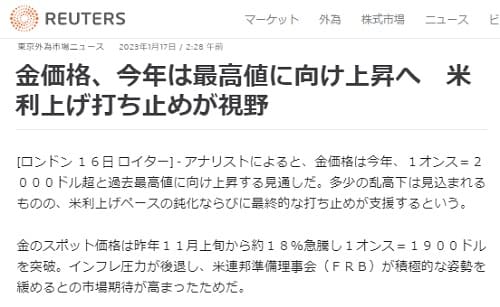


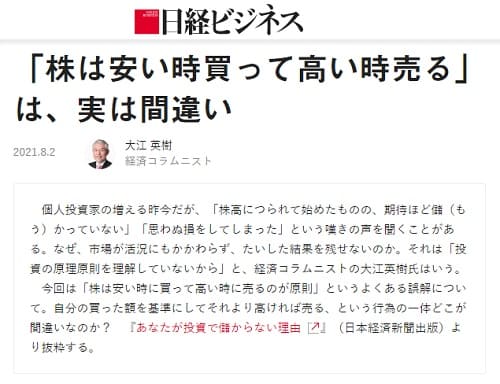
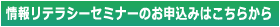

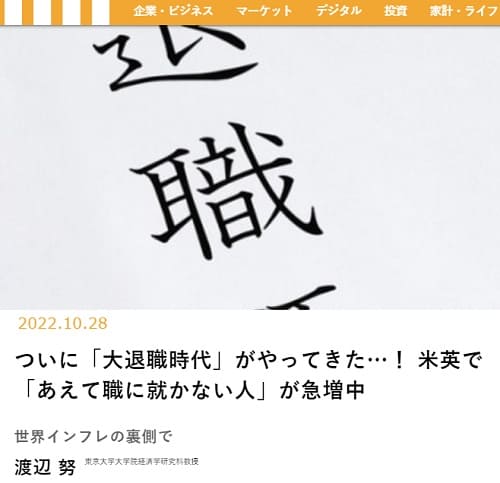
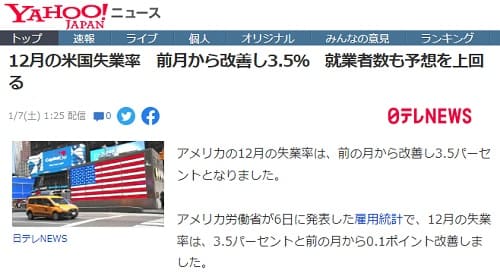



 お問い合わせ
お問い合わせ