|
BRICS首脳会議「共通通貨は見送り」も「拡大は続ける」虚実の背景
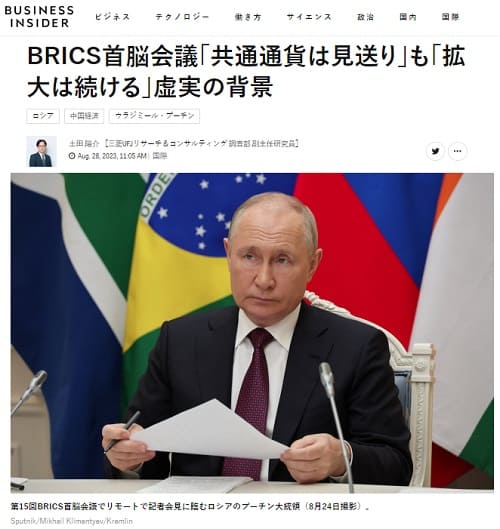
(出典:2023年8月28日 BUSINESS INSIDER)
今回のBRICS首脳会議でも議論された可能性が高い独自の国際決済通貨については、昨年の首脳会議でも発行する計画があることを明らかにしていました。
それから1年が経過し、導入することが簡単ではないことが明らかになりました。もし新しい世界通貨を導入するには、西側の世界銀行やIMFのような組織が必要だということです。また、SWIFTのような国際送金システムも不可欠です。
結局、首脳会議ではこれまで通り、各国がそれぞれの自国通貨を積極的に決済で使うことが強調されました。もし各国が自国通貨を使うと貿易などで仕入れや流通などのコストが高くなりますが、それでも米ドルを使って支配(新植民地主義)されるよりはまだマシなのかもしれません。
6カ国が新規加盟...「拡大版BRICS」はグローバルサウスの代弁者となりうるか?

(出典:2023年8月28日 Newsweek)
BRICSは5ヵ国から11ヵ国に拡大し、中国(人民元)、ロシア(ルーブル)、ブラジル(レアル)、インド(ルピー)、南アフリカ(ランド)の他、アルゼンチン(ペソ)、エジプト(ポンド)、イラン(リヤル)、サウジアラビア(リヤル)、アラブ首長国連邦(ディルハム)、そしてエチオピア(ブル)の決済額が増えていくのは間違いありません。
今後、米ドルやユーロによって散々痛めつけられたアルゼンチンやイランなどの通貨は価値を取り戻し、最終的にユーロのような共通通貨のデジタル版が発行されることになります。つまり、ますます相互貿易を拡大するためのインフラの機能を上げるということです。
その間、「脱ドル化」が急速に進むことはなくなりました。しかし、米ドルが少しずつ世界の基軸通貨としての影響力は失われていくのは確実です。その証拠に、中国とロシアを中心にBRICS経済圏は急速に拡大しています。
中国と「一帯一路」沿線国、貿易拡大が続く背景 ASEAN向けの輸出好調、1~3月期は28%増加

(出典:2023年5月7日 東洋経済ONLINE)
特に、中国の一帯一路は拡大中であり、諸外国との貿易額は前年同期比で約10%増加しています。中国と欧米諸国との貿易額が約5%減少した分を、BRICS加盟国と申請中の国々とで賄っています。
具体的には、EUとは5%減ですが、アメリカは15%減という結果になりました。欧米諸国への輸出を減らした中国は、福島原発の処理水問題で日本からの海産物輸出を全面禁止しましたが、日本への輸出は増やしていくものと考えられます。
一方、加盟国のロシアへの貿易量は約80%増やしました。中国とロシア間には、新たな貨物航路の定期運航が始まり、流氷が解け始めた北極圏を通るルートが取られています。ロシアは中国へ天然ガスや石油、そして穀物を大量に輸送しています。
スエズ運河ルートではなく、北極圏を通る全長7000キロのルートは、これまでの輸送コストを約50%も削減し、移動日数を最大20日も短縮することができるようになりました。貨物船や鉄道、そして道路を利用してユーラシア大陸を行き来するわけです。
サウジアラビア、「ビジョン2030」の目標を上回るペースで成長 年次報告書で詳細発表

(出典:2023年4月28日 ARAB NEWS)
さらに、新たに加盟したサウジアラビアは「サウジビジョン2030」という国家プロジェクトで、経済的、社会的、文化的に多様化を増やすという目標を達成するために、中国の各大都市に直接つながるような仕組みを形成中です。
今年に入り、世界経済の主軸が北米大陸からユーラシア大陸に移動しつつあり、同時に富もアジアに流れ始めています。日本もその一つであり、欧米や中国の超富裕層の移住先として選ばれています。
だからといって、英語も話せない・読めない日本人が彼らと関わることはなく、これまで通り自民党による搾取の対象者として逃げられない運命にあります。今後、どのようにチャンスを見極めることができるようになるのか、まずは世界の潮流を感じてみることです。
| 
